さつまいもっておいしいですよね。炊いてよし、焼いてよし、揚げてよし、加熱するだけでほっくりと甘くなる素敵な食べ物です。
そんな秋の味覚代表であるさつまいもですが、実は長期保存ができるということをご存知でしょうか?
さつまいもは保存温度や環境に気を配れば、家庭でも1ヶ月近く保存することが可能なんです。
その環境に気を配るときに大活躍するのが新聞紙です。
簡単に手に入る新聞紙がさつまいもを保存するのに役立つなんて最高ですよね。
この方法を知っておけば大量にいただいたさつまいもにも困らないし、スーパーで安く売っているときにまとめ買いすることも可能です!
あなたもご家庭にある新聞紙を使って、さつまいもをおいしく長期間保存しちゃいましょう。
さつまいもの保存に新聞紙が適している理由

さつまいもにはいろんな食べ方があるとはいえ、お腹にたまりやすく一度で大量消費しにくい食べ物ではないでしょうか。
その一方で子供が芋掘りで持って帰ってきたり、ご近所さんにいただくことが重なったり、大量に手元にくる可能性が高い食べ物でもあります。

うちも実家から箱で送られてくるので、知り合いに配ってもまだたくさん残っています…
さつまいもは正しい保存方法を知っているだけで簡単に長持ちさせられる食べ物なんです。
その正しい保存方法に選ばれているのが新聞紙です。
どうしてさつまいもの保存に新聞紙が適していると言われているのか、その理由をさつまいも・新聞紙のそれぞれの側から確認してみましょう。
- 保存時の温度が10度以下だと低温障害で変色したり腐る
- 保存時の温度が20度以上だと発芽する
- 水分が触れているとそこから腐る
- 風通しが悪いと呼吸困難で腐る
- 紙は温度の変化を伝えにくいので温度変化が少なくてすむ
- 紙は水分を吸うので吸湿材の役割が果たせる
- 適度に空気を通すので空気が中にこもらない
さつまいもの事情に新聞紙の特徴がぴったりフィットしているのがおわかりいただけたと思います。
さつまいもを新聞紙で包んで涼しい室内におくだけで、長期保存が可能なんです。
スーパーで売っているような土のついていないさつまいもだと、これから紹介する方法で1ヵ月ぐらい保存することが可能です。
芋ほりや家庭菜園で手に入るような土付きのさつまいもだと、なんと3ヵ月近く良好な状態で保存できます。

それだけ時間があればすこしずつ使っていっても捨てることなく食べきることができますね。
新聞紙を使った保存の手順
それでは具体的にどうやって保存するのがいいか説明していきますね。
- さつまいもは洗わずに1本ずつ新聞紙で包む
- もし量が多ければ段ボールにまとめる
- 室温が15度くらいの場所に置いておく
たったのこれだけです。忘れてはいけないのは『さつまいもを水で洗わない』ということ。
さつまいもは水に弱く、水分がついたまま保存しようとするとそこから簡単に腐ってしまいます。
さらに洗うときの衝撃で表面が傷つき、そこからいたんでしまうこともあるんです。
新聞紙で包むのはそういった表面への刺激を和らげるという意味もあるんですね。
さつまいものまわりの土は水分・接触の対策にもなるのでついたままの方がいいんです。
土がついたままのさつまいもなら、この保存方法で3ヵ月も保存できるんだとか。
スーパーで売っているさつまいもは一度洗浄されてしまっているので、1ヵ月ぐらいを目途(めど)に食べきってくださいね。

まとめておいておくのは段ボールじゃないとダメなの?
段ボールは紙製品なので、新聞紙と同じでさつまいもの事情にぴったりあっています。
なので段ボールを使うのがおすすめ、というわけです。
発泡スチロールの箱やビニール袋でもいいのですが、どちらも空気の循環を妨(さまた)げる素材でできています。
そのため、底や横側に空気穴をたくさん開けて、空気の通り道が確保できるようにしてくださいね。
新聞紙がない場合はキッチンペーパーを使おう
新聞紙が最適と言われても、手元にはないという方も多いのではないでしょうか。

我が家では新聞は取ってないし、そのためにわざわざ買うのはちょっと…
そんな場合におすすめできるアイテムが2つあります。
それはキッチンペーパーと地域情報誌です。とくにキッチンペーパーならあなたの台所にも常備されているのではないでしょうか?
新聞紙に比べると割高ではあるのですが、さつまいも数本ならキッチンペーパーで十分事足ります。
使い方も新聞紙と同じようにきっちり包んでおくだけで大丈夫です。

地域情報誌ってなんだっけ?
郵便受けをのぞくと無料のタウン誌が届いていることがありますよね。
地域のお得情報やいろんなお店の宣伝がのっているあれです。
地域情報誌も紙製品なので、新聞紙と同じように使うことができます。
無料で勝手に渡される情報誌なら、負担に感じることなく使えるのではないでしょうか。
他にも割れ物の処分や梱包のクッションなど、地域情報誌には「じゃない」使い方がたくさんあります。
さっと読んで捨ててしまう方も、少しおいておくと何かと便利ですよ。
また、ラップやさつまいもが入っていたビニール袋は新聞紙の代用になりません。
ラップは空気も水分も通しにくい素材でできています。
中のさつまいもが呼吸できなくなって、そのうえ自分から出た水分をラップの中にため込んでしまうんです。
実体験から言うと、買ってきたビニールのまま放置すると本当にあっという間に腐ってしまいます…
ビニールの口を切って開けっ放しにしたり、いっそ何にも入れない方がまだマシです。
かといってその状態だと、やはりカビが生えてきていたんでしまうことは多々あります。
長期保存するとわかっているときは、やはり新聞紙などに包んでおくと安心です。
さつまいもの保存に適した温度の場所を探そう

さつまいもの保存場所は10度以上、20度以下といわれていますが、具体的にどこがいいのでしょうか?
考えられそうな場所の温度を調べてまとめてみました。
冷蔵庫内
- 冷蔵庫…2度~5度
- 野菜室…3度~8度
- チルド室…0度
- パーシャル…-3度
- 冷凍庫…-18度
人が快適に感じる室温
- 夏…25度~28度
- 冬…18度~22度
このように、冷蔵庫や冷凍庫はもちろん、人が快適に過ごしている室内でもさつまいもにとっていいとは限りません。
さつまいもを長期保存することが多い秋・冬なら、廊下に出しておくとさつまいもにとってほどよい温度であることが多いです。

我が家では玄関廊下に置かれていることが多いです。
とはいっても、外が寒すぎると廊下という屋内であっても冷えこみすぎることがあります。
たとえば外気温が5度のときの室内は、暖房をいれないと10度以下まで下がってしまいます。
そんな寒すぎる時期は、人が活動している場所に近いキッチンにおくのがおすすめです。
ほかにもあなたのご家庭ではここだ!という場所を探してみてください。
適した場所がないときは冷凍保存を活用しよう

夏はどこにおいても20度超えなんだけどどうすればいいの?
暑すぎる・寒すぎるときは、どう調整しても適した温度の場所がないことがあります。
そんな場合は方向転換をして、冷凍保存に切り替えましょう。
この場合でも1ヵ月から3ヵ月と常温保存したときと同じくらい長持ちさせられます。
なお、さつまいもを冷凍保存する場合は一度加熱することを強くおすすめします。
あく抜きをすれば生のまま冷凍できる、という意見もあります。
ですが生のままだと結局低温障害が起こってしまうんです。食感も味も悪くなり、長期保存にはやはり向きません。
なので一度加熱してから冷凍しましょう。しっかり冷ましたさつまいもを、ラップや保存用バッグに包めば問題なく冷凍できます。
さらに使用用途にあわせて切っておくと、より便利です。
私が特に使い勝手がいいと感じる切り方は次の3通りです。
天ぷらや煮物向け。解凍してから切ったりつぶすことによって他の料理にも転用可能。
さつまいもご飯やシチューに。甘煮にしてパイのフィリングにするのも目先が変わっておすすめです。
付け合わせやサラダに。離乳食やお菓子作りにも使えます。
他にもスティック状にして芋けんぴや大学芋にしたり、薄切りにしてお味噌汁にいれたり、あなたの使いやすい切り方で冷凍してくださいね。
冷凍したさつまいもの解凍方法
他の食材を冷凍したときと同じように、さつまいもも低温でじっくり解凍します。
手順もシンプルで使う前日に冷凍庫から冷蔵庫に移すだけ、というもの。
ゆっくり解凍されるので風味を損なうことなく、おいしいまま解凍できます。
天ぷらや煮物など再度加熱する料理の場合は凍ったまま調理することもできます。
煮物はむしろ冷凍した方がキレイな発色を保てて、しかも素早くできあがるんですよ。
また、焼き芋を冷凍した場合は半解凍でアイスのように食べるのもおすすめです。
冷凍庫から出して室温で10分ほどおいておくだけでスプーンですくえるようになります。
冷凍するときに少し手間がかかる分、調理するときにはひと手間省ける冷凍保存。
真冬や真夏の常温保存できないときには、ぜひ試してみてください。
さつまいもを保存してカビや黒ずみがでてしまったとき

さつまいもを大量保存していると、どうしても全部を良好に保つことはできないこともあります。
さつまいもをきっちり新聞紙で包んだはずなのに、あけてみたら様子がおかしい…
そんな場合は原因がなにか突き止め、適切な対処法をとりましょう。
変色
さつまいもが黒っぽくなっている、いわゆる黒ずみは低温障害がおきてしまったことが原因です。
黒ずんでいる部分を大き目に切り落とせば残りは食べられます。
全体的に黒くなってしまっていたら、残念ですが諦めましょう。
なお、黒いかさぶた状のものはヤラピンというさつまいもの成分です。食べても問題ありません。
カビ
高温多湿の環境下だとカビが生えることがあります。
白カビや青カビは、さつまいものようにみっしりと詰まった食べ物に根を伸ばすのは苦手です。
なので少ししか生えていない段階ならば、カビの部分を切り落として食べることが出来ます。
ただし白い綿状のカビと黒カビはもう手遅れです。毒性が強いので絶対に食べないように気をつけてください。
腐敗
柔らかくなっていたりべとべとしていたり、逆に水分がぬけてスポンジのようになっているときは腐っています。
食べると苦味や酸味など、さつまいもではない味を感じることになります…
調理しても腐っているものはどうしようもないので食べられません。
発芽
20度を超える環境だと、さつまいもから芽が出てしまうことがあります。
じゃがいもの芽と違い、さつまいもの芽に毒性はありません。むしろ食べられます。
もちろんさつまいも本体も問題なく食べることができます。
ただし発芽するのにさつまいも本体の栄養を使ってしまうので、甘みも抜け味は落ちてしまいます。
さらにそのままほおっておくと水分も抜け、しわしわになってしまいます。
発芽していることに気付いたら早めに食べきった方がいいです。
まとめ

- さつまいもの保存には新聞紙がジャストフィット
- さつまいもを保存するときは洗ってはいけない
- 新聞紙で包んで涼しいところにで保存する
- 適した場所がないときは加熱して冷凍する
- いたんでいるさつまいもはあきらめるのが無難
- 発芽したさつまいもは食べられる
さつまいもの保存に新聞紙を使うと、生のまま1ヵ月も長持ちさせることができてしまいます。
とても便利なこの方法で、おいしいさつまいもをいつでも食べられるようにしましょう。
ただし、いたんださつまいもには気をつけてくださいね。
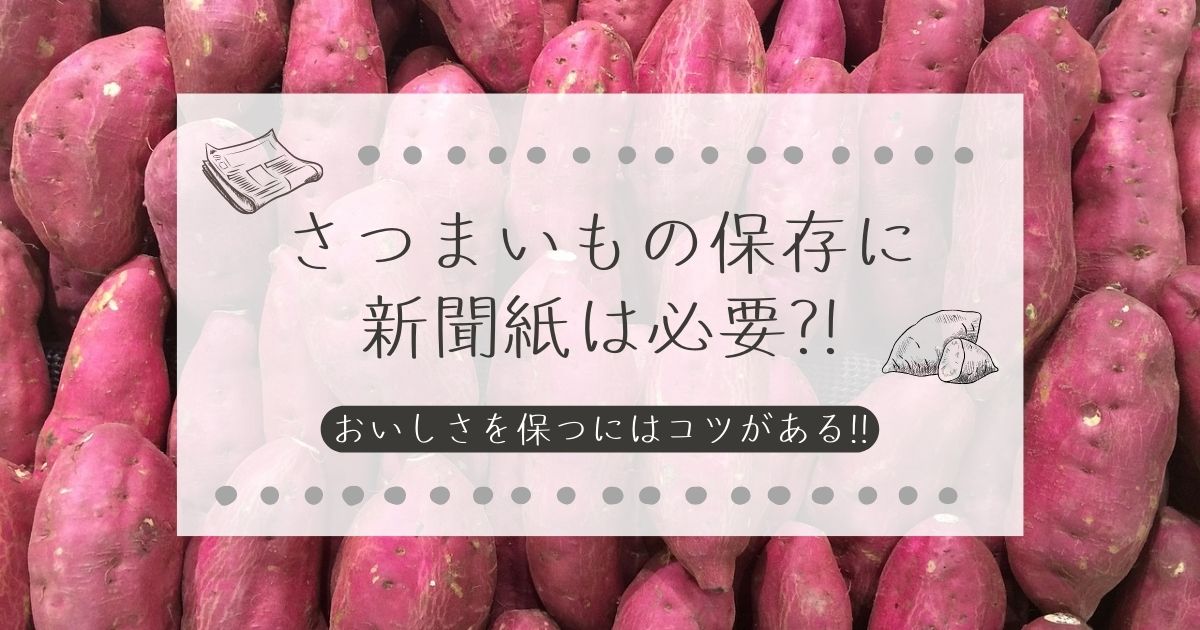


コメント